ElectroHarmonix Blackfinger
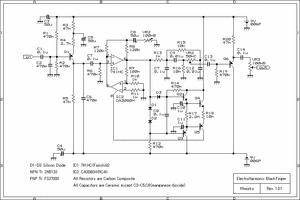
<回路全体の構成>
入力信号は、Q1で入力を増幅した後(交流的にはR5/R4倍(約17.4倍))、IC1/IC2のVCAユニット、BigMuffタイプのトーン回路を経てQ6の出力バッファへ流れます。VCAユニットの後ろに信号レベル検出回路がついているフィードバック型の構成のコンプレッサーになります。
<信号レベル検出回路について>
VCAユニット後ろにつながる検出回路は、D1-D2方面とD3方面に分かれます。この辺何故非対称なのかは不明です。ダイオードが2つだと反応し過ぎ・4つだと反応しなさ過ぎということで現物合わせ的に決定されたのかもしれません。
D1-D2,Q3により振幅の下側が増幅され、C10で平滑化されてQ5に至ります。また、振幅の上側についてはD3,Q2により増幅され、C11で平滑化されてQ4に至ります。そして、Q4とQ5にはさまれたR18にかかる電圧と抵抗値により決まる電流がQ5のコレクタから放出され(Q5のベース電流は比較的小さいので無視)、OTA(OperetionalTransconductanceAmplifier:トランスコンダクタンスアンプ)のIabc(アンプバイアス電流=OTAのトランスコンダクタンスを制御する電流)となります。
ちなみに、R18の両端には電源電圧(9V×2=18V)を超える電圧がかかることはないので、Iabcは最大でも18V÷10k=1.8mAとなり、絶対定格(2mA:HarrisCA3080データシートより)を超えることはありません。
この際、D1-D3の順方向電圧降下およびQ2-Q5のVbeより、入力がない場合はR18には電圧がかかりません。理由は、入力がゼロの場合、Q2,Q3のベース・エミッタ間電圧VbeとD3,D2の順方向電圧降下が概ね相殺され、Q4,Q5において、それぞれのVbeの合計(=R17にかかる電位差)がD2の順方向電圧降下分程度しか確保できないためOFFになり、コレクタ→エミッタに電流が流れないことによります。
信号が検出回路に入力された場合、前述のように振幅の上側はD3,Q2,C11,Q4により、振幅の下側はD1-D2,Q3,C10,Q5により検出→平滑化→増幅されてR18の両端電圧になります。その際波形が対称ならば、D2ひとつ分のオフセットのため、Q4のエミッタ−アース間電位 > アース−Q5のエミッタ間電位となります。結果として、検出回路全体では上下非対称の動作をすることになります。
C8により検出回路への入力のうち高周波成分がカットされます。カットオフ周波数は、D1-D3の存在により見えにくくなっていますが、概ねC8およびIC1/IC2によるVCAユニットの出力インピーダンスにより決まるのではないかと思います。
また平滑化の時定数は、C10,C11およびR17によって決定されるものと思われます。
(T=C10×R17/2ぐらいかな???)
<VCAユニットについて>
特徴としては、OTA(IC2)をそのまま信号経路に使わないで、IC1のフィードバック経路に使っている点があります。VCAは反転入力と非反転入力の差動入力電圧をなるべく少なくしないと出力が歪んでしまうため(せいぜい±5-10mV程度。計算は下記<差動入力電圧範囲の試算>参照)、直接信号経路に使った場合は、信号を一度十分アッテネートした後で再度増幅する必要があります。
この回路のようにOTAをフィードバック経路に使うことで、Q1を出た信号をアッテネートすることなくIC1にぶち込むことができます。しかしフィードバック経路にあっても、結局はR9/R10によりアッテネートしないとIC2の入力が飽和してしまいますが。さらにR9/R10に対してR11をセットしてなるべくオフセット等が少なくなるようにしているようです。
このアイデアがどの程度有効かについては、下記<BlackFinger型VCAユニットの検証>で計算してみます。
そういえば、IC2を無視するとIC1周りはT型帰還回路になっていることに気づきます。この形の回路は昔のアンプの初段増幅で使われているのを見た事があります。参考文献1にあるT型帰還回路におけるY-Δ変換を行って計算すると、交流ゲイン(つまりC8を無視)は120k/VR2倍(1.2〜オープンループゲイン倍)となります(実際には先ほど無視したIC2(OTA)もフィードバックに関与するので、本当にオープンループゲイン倍になるわけではない)。
下記<BlackFinger型VCAユニットの検証>での計算結果から考えるに、T型帰還回路とOTAのフィードバック回路を組み合わせることにより、巧妙にダイナミックレンジを稼ぎつつ歪みを抑え、かつソフトニーなコンプレッション特性を得ているようです。
ちなみに、もう少し後の機種では、IC2の非反転入力と反転入力を比較的低い値の抵抗でつなぎ、さらに反転入力とアースの間に大容量のコンデンサ(数〜数十μF程度)をつなぐような回路も採用されています。
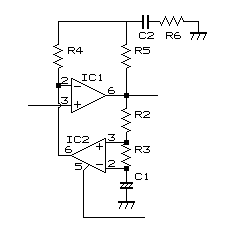
<欠点>
実はこのBlackfinger、6弦を思いっきり弾いたりコードを掻き鳴らしたりすると音が消えます。
そういう「仕様」なのでしょうがないといえばしょうがないのですが、この現象は、Q1のバイアスが正電源側に寄りすぎているかエミッタ抵抗が大きすぎるかのためにコレクタ電流が十分に取れず、大きい入力信号に対して波形の片側がクリップしてしまう(飽和領域での動作となる)ことが原因で起こっているようです。この辺りの状況については下記<Q1の動作検証>に詳しく書きます。
(r0r0さんご教示ありがとうございました)
また、他のコンプのように電流を供給源Q5とOTAの5ピンとの間に可変抵抗をつなぐことで、Iabcの変化範囲を適度にコントロールできるようになります。
上記の改善策については、MODの項をご参照ください。
<CA3080の回路解析>
HarrisCA3080データシート中の Schematic Diagramより、D1,Q3はカレントミラー回路になっているので、ID1=Q3のコレクタ電流IC3と考えることができます。(ダイオードの飽和電流は、参考文献2によると10-16から10-10Aとのことなので、ここでは無視する)
よって、Q3のhFEをhFE3とすると、Iabc(アンプバイアス電流:Amplifier Bias Current)は、
Iabc=ID1+IB3
=IC3+IC3/hFE3
={(hFE3+1)/hFE3}・IC3
トランジスタのhFEは通常100程度はあるので、(hFE3+1)/hFE3≒1と考えることができます。
∴Iabc≒IC3・・・(1)
Q1のコレクタ電流IC1およびQ2のコレクタ電流IC2とIC3の関係は、Q1とQ2のhFEをそれぞれhFE1, hFE2とすると、
IC3={(hFE1+1)/hFE1}・IC1+{(hFE2+1)/hFE2}・IC2
例によってトランジスタのhFEは100程度なので、(hFE1+1)/hFE1≒1,(hFE2+1)/hFE2≒1と考えることにします。よって、
IC3≒IC1+IC2
上式および(1)の結果より、
∴Iabc≒IC1+IC2・・・(2)
よって、IabcはほぼIC1とIC2の合計に等しくなります。
この時、Q8,Q9がダーリントン接続なのでQ7,D3(多分D5の誤植),Q8,Q9は全体としてウイルソン型カレントミラー回路として働く(D4はQ8のE-B間保護用。通常は非導通)ため、結果として、Q8,Q9の出力電流=IC2 となります。
同様に、Q5,Q6がダーリントン接続なのでQ4,D3,Q5,Q6は全体としてウイルソン型カレントミラー回路として働きます(D2はQ5のE-B間保護用。通常は非導通)。ただし、このまま出力をつなぐと全波整流回路になってしまうので、この出力をさらにQ10,Q11,D6によるウイルソン型カレントミラー回路によって反転して出力しています。よって、Q10の出力電流=-IC1(極性が反対になっていることに注意)となります。
よって、IC全体の出力電流Ioutは、Q8,Q9の出力電流とQ10の出力電流の和に等しいので、
∴Iout=IC2-IC1・・・(3)
(2)および(3)より、出力電流IoutとIabcの関係は、以下のようであることがわかります。
|Iout|≦Iabc (等号はIC1もしくはIC2のいずれかがゼロの時に成立する)
つまり、Ioutの最大振幅はIabcによって決まる、ということです。
<差動入力電圧範囲の試算>
差動入力回路におけるペアトランジスタQ1,Q2のコレクタ電流IC1,IC2は、参考文献3:pp39-40にある通り、以下のようになります。参考文献3中のVID,IC5はそれぞれVin,IC3に対応します(IC1,IC2はそのまま)。
IC1=IC3/2・{1-tanh(x)}
IC2=IC3/2・{1+tanh(x)}
x=Vin/2VT
(VT:熱電圧 接合部温度T=300Kのとき25.85mVとなる)
上の式をグラフ化したのが下図です。
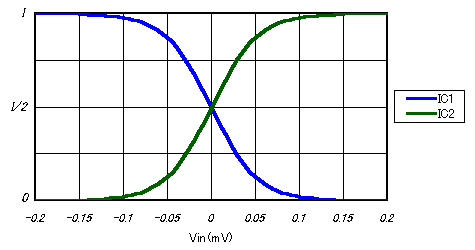
グラフより、差動入力電圧の絶対値が大きくなればなるほど入出力のリニアリティーが失われる(つまり歪みが増える)ことが直感的に見てとれます。(見てとってください)
次に、差動入力電圧がどれくらい大きくなるとどれくらい歪むのかを定量的に示してみます。
(1)および(3)の結果を考慮すると、出力電流Ioutは以下の通りになります。
Iout=IC2-IC1=IC3・tanh(Vin/2VT)
≒Iabc・tanh(Vin/2VT)
トランスコンダクタンスGmは、出力電流Ioutおよび差動入力電圧Vinを用いて以下の通り表すことができます。
Gm=dIout/dVin=dIout/dx・dx/dVin
dIout/dx=Iabc・1/cosh2(x)
dx/dVin=1/2VT
∴Gm=Iabc・1/cosh2(x)・1/2VT=Iabc/2VT・1/cosh2(Vin/2VT)
よって、原点(Vin=0)ではcosh(0)=1なので、Gm(0)=Iabc/2VT=19.38・Iabc(T=300Kのとき)となります。
この時、Gm(0)に対するGmの誤差を±a%以下にすることを考えてみると((100-a)%≦Gm/Gm(0)≦(100+a)%)、
Gm/Gm(0)=Iabc/2VT・1/cosh2(Vin/2VT)/(Iabc/2VT)=1/cosh2(Vin/2VT)
cosh(x)≧1より、1/cosh2(Vin/2VT)≦100%となり、Gm/Gm(0)は100%を上回ることはないので、下限(100-a)%だけ考えればよいことになります。
Gm/Gm(0)=1/cosh2(Vin/2VT)≦(100-a)%
1/(1-a/100)=cosh2(Vin/2VT)
Vin/2VT=arccosh((1-a/100)-1/2)
∴Vin=2VT・arccosh((1-a/100)-1/2)
上の式をもとにExcelで実際の値を計算してみました。
許容誤差aを1%すると、許容差動入力電圧範囲Vinは±5.187mVとなります。また、許容誤差aを5%すると、Vinは±11.759mVとなります。思った以上に狭くてびっくりです。
<BlackFinger型VCAユニットの検証>
まず、IC1周りはT型帰還回路となっているので、参考文献1にあるY-Δ変換を行ってπ型帰還回路に変換します。
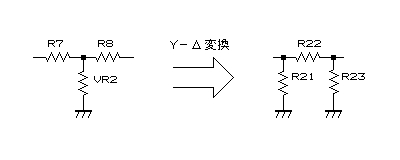
今回は交流特性のみ考えることにしてC8を無視すると、結果は以下のようになります。
R21=R7+2・VR2=120kΩ+2・VR2
R22=(R7・R8+R7・VR2+R8・VR2)/VR2=240kΩ+120kΩ2/VR2
R23=R8+2*VR2=120kΩ+2・VR2
IC1の出力電位をVout、OTA(IC2)の非反転入力の電位をVa、IC1の反転入力の電位をVinと置くと、VCAユニット全体の増幅率Avを求める式は以下のようになります。
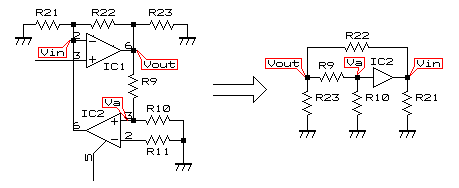
Va=R10/(R9+R10)・Vout=1/101・Vout
Ia=Va・Gm=Gm/101・Vout (Gm:OTA(IC2)のトランスコンダクタンス,Ia:OTAの出力電流)
Vin=If・R21+Ia・R21 (If:帰還抵抗R22を流れる電流)
Vout=If・(R22+R23)+Ia・R21
Av=Vout/Vin
以上の連立方程式を解くと、
Vout=If・(R22+R21)+Ia・R21=If・(R22+R21)+Ia・R21
Vout-Ia・R21=If・(R22+R21)
(1-(Gm・R21)/101)・Vout=If・(R22+R21)
∴If=(1-(Gm・R21)/101)/(R22+R21)・Vout
Vin=If・R21+Ia・R21=(If+Gm/101・Vout)・R21
=((1-(Gm・R21)/101)/(R22+R21)・Vout+Gm/101・Vout)・R21
=((1+(Gm・R22)/101)/(R22+R21))・R21・Vout
∴Av=Vout/Vin=(R22+R21)/((1+(Gm・R22)/101)・R21)
=101・(R22+R21)/((101+(Gm・R22))・R21)
この時、OTAをなるべく歪まないように使うことを考えます。<差動入力電圧範囲の試算>での結果からすると、OTAの入力が±5.187mV以内ならば(R9/R10により1/101にアッテネートされることを考えると、IC1の出力±5.187mV×101=±523.8mVならば)、OTAによる信号の歪みを1%以下に抑えることができるはずです。
このような条件でOTAを使用することにより、誤差1%の範囲内でGm≒Gm(0)=Iabc/2VT=19.38・Iabc(T=300Kのとき)と考えることができるようになります。
∴Av=101・(R22+R21)/((101+(19.38・Iabc・R22))・R21)
以上の結果を踏まえて、VR2を1kΩ,10kΩ,100kΩとしたときのIabcと出力の関係のグラフをExcelで書いてみました。簡単のため入力信号とIabcは比例することとしたので、出力はn×Iabc×Avの形になるはずです。今回はグラフの形を見たいだけなので、y軸をIabc×Avとして(nを省略して)グラフを書いてみました。
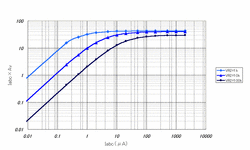
結果を見るに、入力に対してきれいにソフトニーな反応をしていることがわかります。また、VR2の抵抗値を小さくして行くと、徐々にコンプレッサーが深くかかるようになっています。
つまり、入力信号の絶対値にキレイに比例する電流を出力するような入力信号検出回路を使い、かつ通常の使用ではIC1の出力が±523.8mVを超えないように設定すれば、十分使いモノになりそうな予感です。
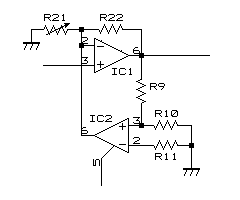
参考までに、T型帰還回路を採用せず、上図のようにR22を固定かつR21を可変して増幅率を調整するような回路構成とすると、以下のように、VR2の値を変えても圧縮の度合をコントロールすることができなくなります。(上:R22=500k,下:R22=∞Ω)
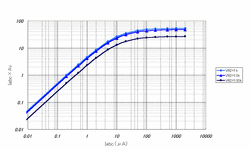
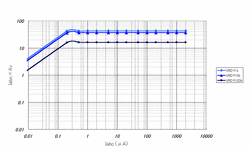
なるほどT型帰還回路を採用した意味がよくわかる結果となっているように思います。
<Q1の動作検証>
大きい信号を入力した際にQ1がどのように動作するかを考察したいと思います。
Q1のベース電流をIb, R1に流れる電流をIBIASとすると、
VCC=R1・IBIAS+R2・(Ib+IBIAS)
VCC=9V,R1=R2=470kΩ なので、
2・IBIAS+Ib=9V/470kΩ
IBIAS=4.5V/470kΩ-Ib≒9.574μA-Ib
Q1のコレクタ電流をIc,エミッタ電流をIeとすると、
Ic=hFE・Ib
Ie=Ic+Ib=(hFE+1)Ib
Q1のエミッタ電位をVe,ベース電位をVbとすると、
Ve+Vbe=Vb
オームの法則よりVe=(R3+R4)・Ie,Vb=R1・IBIASなので、
(R3+R4)・Ie+Vbe=R1・IBIAS
Ie/(hFE+1)=Ib,IBIAS=4.5V/470kΩ-IbよりVbe=0.6Vとすると、
(R3+R4)・(hFE+1)Ib+0.6V=470kΩ・(4.5V/470kΩ-Ib)
(R3+R4)・(hFE+1)Ib+0.6V=4.5V-470kΩ・Ib
(R3+R4)・(hFE+1)Ib+470kΩ・Ib=4.5V-0.6V
(R3+R4)Ie+470kΩ/(hFE+1)・Ie=3.9V
((R3+R4)+470kΩ/(hFE+1))・Ie=3.9V
∴Ie=3.9V/((R3+R4)+470kΩ/(hFE+1))
R3=47kΩ,R4=2.7kΩより、
Ie=3.9V/((47kΩ+2.7kΩ)+470kΩ/(hFE+1))
Ie=3.9V/((49.7kΩ)+470kΩ/(hFE+1))
hFE=100とすると、
Ie=3.9V/((49.7kΩ)+470kΩ/(100+1))
≒71.7μA
つまり、エミッタには最大でも71.7μAしか電流が流れない
→ (Ib≒Icと考えると)コレクタからは71.7μA×47kΩ≒3.37Vppしか電圧を取り出せない
ということになります。
(それ以上の電圧を無理やり取り出そうとするとトランジスタが飽和(クリップ)する)
Q1の交流増幅率はおおむねR5/R4≒17.4倍になりますので、ベースに加える信号が電圧ベースで3.37Vpp/17.4≒0.194Vppを超えると、波形の下側がクリップすることになります。
波形の片側がクリップした状態で信号レベル検出回路に信号が流れると、実際の出音とレベル検出回路における検出結果との間のバランスが崩れます。実際にはレベル検出回路が過剰反応を起こす(ほぼ波の大きい側のレベルで判定される)ことで、結果として音が消えるような現象が起きているようです。
レベル検出回路の検出結果(Iabc)を制御するような可変抵抗を入れることによってもある程度の操作性の向上は見込まれます(可変抵抗の位置によって音が消えないセッティングが可能になる)が、Q1で波形がクリップすることが音が消える根本的な原因なので、波形がクリップしない程度にQ1に流れる電流を増やすことこそが回路的に最も望ましい解決策となります。実装上はR3を15kΩ程度に減らしてやるとよいようです。
実装の詳細は、MODの項をご参照ください。
参考文献1:トランジスタ技術SPECIAL増刊:OPアンプによる実用回路設計(馬場 清太郎著、CQ出版社)
参考文献2:はじめてのトランジスタ回路設計(黒田 徹著、CQ出版社)
参考文献3:解析OPアンプ&トランジスタ活用(黒田 徹著、CQ出版社)